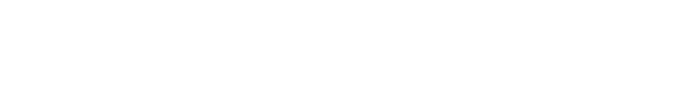
 子供の頃から関西へ行くことが多かった私にとって、近江は極めて親しい国であった。岐阜を過ぎてほどなく汽車は山の中に入る。やがて関ヶ原のあたりで、右手の方に伊吹山が姿を現すと、私の胸はおどった。関西へ来た、という実感がわいてきたからである。大和絵のような丘を縫って、平野へ出ると、霞のあなたに琵琶湖が見えつかくれつし、その向うに比良山が横たわっている。雪の頂いていることが多かった。つづいて比叡山、そして京都。何十ぺん、いや何百ぺんとなく見た景色であったが、それは汽車の窓から横目で見てすぎただけのことで、近江は長い間未知の国にひとしかった。
子供の頃から関西へ行くことが多かった私にとって、近江は極めて親しい国であった。岐阜を過ぎてほどなく汽車は山の中に入る。やがて関ヶ原のあたりで、右手の方に伊吹山が姿を現すと、私の胸はおどった。関西へ来た、という実感がわいてきたからである。大和絵のような丘を縫って、平野へ出ると、霞のあなたに琵琶湖が見えつかくれつし、その向うに比良山が横たわっている。雪の頂いていることが多かった。つづいて比叡山、そして京都。何十ぺん、いや何百ぺんとなく見た景色であったが、それは汽車の窓から横目で見てすぎただけのことで、近江は長い間未知の国にひとしかった。
(白洲正子『近江山河抄』、平成6年、講談社文芸文庫、7頁)
「親しい国」であると同時に、いまだ「未知の国」であるとも述懐される「近江」の地、そのような思いはところで、多くの日本人にとっても依然として変わらないのかもしれません。引用した文章は昭和49年に白洲正子が上梓した『近江山河抄』のまさに冒頭の一節です。そこにある汽車を新幹線に置きかえてみてください。いまだに近江は、東京と京阪神を結ぶ沿線上の、窓から眺められるだけの未知なる土地なのかもしれません。
数年前にNHKドラマスペシャルで放送され、巷の話題をさらった「従順ならざる唯一の日本人」白洲次郎の妻として、多くの日本人の脳裏に刻まれた彼女はそれと同時に、河上徹太郎や小林秀雄の勧めで読みふけったフランス文学の良き理解者であり、4歳という俄かには信じられないような若さで習い始めた能、青山二郎の影響のもと始めた骨董、流派に属すことを嫌い、独自の美を築いた生け花、その他あらゆる日本文化のあれやこれやに通暁した、類まれな美的感性の持ち主でもあり、そしてまた14歳で早くも渡米、留学を果たした早熟の国際人でもありました。このような多面的な顔を持つ正子はしかし、それまで「見てすぎただけ」の近江を、足繁く通ううちに、こよなく溺愛し始めます。毛利志満コラム、第一回目は、「近江は日本文化の発祥の地といっても過言ではない」とまで豪語した粋人、白洲正子に照明を当て、なかでも毛利志満が本店を構える土地、古くは蒲生野と呼ばれた近江平野一帯とそこを舞台にした万葉集のとてもとても有名な歌について語りたく思います。
エッセイ『近江山河抄』は、近江について白洲正子の単なる想いを徒然に綴った随想というよりも、本来、フランス語でエッセイ(essai)が「試み」を意味しているように、正子自身がその足を実地に運ぶことでようやく生みだされた果敢な試行錯誤の賜物であるように思います。そして、『平家物語』や『枕草子』といった日本の古典文学を若いころから愛読していた正子の興味が、万葉集のなかでも最も人口に膾炙した歌の詠まれた土地、近江は蒲生野に向かったのも必然の糸に導かれてであったと言っても過言ではないでしょう。
天皇、蒲生野に遊猟したまふ時、額田王の作る歌
あかねさす紫野行き標野(しめの)行き
野守(のもり)は見ずや君が袖振る
(あかね色を帯びた、あの紫の野や御料地をあちらへこちらへと行ったりして、
野の番人が見るではないですか、あなたがお袖をお振りになるのを)
実際のところは分かりませんが、後世によって絶世の美女というイメージを作り上げられた額田王、彼女のこのような歌に対して、大海人皇子はこう切り返します。
皇太子の答へましし御歌
紫草(むらさき)のにほへる妹(いも)を憎くあらば
人妻ゆゑにわれ恋ひめやも
(紫の色のように艶やかなあなたを憎いと思うのならば、
人妻であるのに、どうして私が恋い慕うことがあるでしょう)
正子が万葉集を代表するほど著名なこの相聞歌から何を聴き取り、どのように想像の羽を伸ばしたのか、そのことの前に歌の背景に少しだけ触れておきましょう。
才色兼備を絵に描いたような女性、額田王(ぬかたのおおきみ)と天智天皇(中大兄皇子)の弟、大海人皇子(おおあまのおうじ)の間で取り交わされた贈答の歌を理解するにはまず、そのあまりにも有名な三角関係を考慮に入れておく必要があります。当初、額田王は大海人皇子との間に十市皇女(とちのひめみこ)をもうけましたが、この歌のやり取りが行われた天智7年(668年)5月5日当時はすでに天智天皇のもとに召されていた女性でした。つまりこの二人の歌のやり取りは、かつての恋人同士が往時のラブロマンスの炎がいまだ灯火ながら燃え続けていることを、「袖を振る」という求愛の身振りを介して、暗に語っているのです。それも、いまや人の妻であるにもかかわらず。それゆえ、私たちはこの歌から「忍ぶ恋」の密やかな告白を空想しがちですが、残念ながらそれは必ずしも史実に即したものとは言えないようです。
大岡信氏の『古典を読む 万葉集』はじめ、現代の多くの万葉集に関する研究書が述べているように、この歌で詠まれている近江の蒲生野での「遊猟」(みかり)とは毎年5月5日に催される慣習だった薬狩りのことで、諸国の王や大臣のほか、主要な人々が参加した一種のお祭りでした。ところで、天智7年といえば、中大兄皇子が大和の飛鳥から大津に遷都し、天智天皇として正式に即位した翌年にあたります。彼らは、大津京から琵琶湖を船で渡り、現在の近江八幡市の牧にて上陸、狩りをいまかいまかと待ちわびる大勢の官人たちと共に馬にまたがり、蒲生野を目指しました。男性は鹿の鹿茸(ろくじょう)を、女性は薬草を採り、宮廷人はみな華やかな衣装でこれに加わったようです。そして、この年中行事が執り行われた後に、盛大な宴が催され、そのような無礼講の宴席を盛り上げようと人々の面前で歌われたのがこの贈答歌であったのです。
ですから、「掛け合いの内容そのものは忍ぶ恋だが、それが披露され、賞でられた場は、衆人環視の場であった」
(大岡信『古典を読む 万葉集』、2007年、岩波現代文庫、35頁)
ということになるわけです。歌にだけ耳を澄ませば聴こえるはずのなかった雑音?のように思われるかもしれませんが、おそらく周りを囲う事情に通じた人々からは拍手喝采、やんややんやとひやかしの声が途絶えなかったことでしょう。
さて話を正子が感じとった「あかねさす…」に戻しましょう。彼女もまた以上に触れたような「色気のない話」になってしまったことに肩を落としながらも、それでもやはり歌の方には色気が「ありすぎる程ある」と語っています。
自然描写など一つもないのに、紫に霞む近江平野を、散策する人々の姿が目に浮ぶ。実際にも湖東の岡の上に立って蒲生野を見渡す時、私たちは「あかねさす…」と口ずさまずにはいられない。比叡山に日が落ちると、一瞬あたりはあざやかな夕焼に染まり、やがて山の影も、川の流れも、紫の靄の中にとけこんで行く。
(白洲正子『近江山河抄』、120‐121頁)
さりげなく件の相聞歌を補足するように点描されたこのきめ細やかな情景は、悠然といまだ変わらず蒲生野の風景として、そして6月の、この頃の夜ともなれば蛍の乱舞でちらほらと飾り立てられた光景として、蒲生野に暮らす人びとにとってはお馴染みのものです。ところで、エッセイ『近江山河抄』に収められた「あかねさす 紫野」の話題は万葉時代から唐突に離れ、正子がひょんなきっかけで目の当たりにし、一目惚れしたある「美しい童子の首」の方へと展開していきます。もちろん、唐突に、といっても話は繋がっています。この童子の首が掘り出されたのが、他でもない蒲生野にある「雪野寺」(龍王寺)であったからです。現地に赴く機会を逸しながら二、三十年の歳月が流れ、十二月にしては暖かいとある日、ようやく正子に雪野寺詣出のチャンスが巡ってきます。
朝早くから京都の宿を後にしたのは良かったものの、その日「琵琶湖の周囲は霧が深く、三上山も今日は見えない」ような天候。それでも、鏡山に沿いながら南下、竜王町の在所である須惠、薬師を通過し、川守で車を乗り捨てます。「川守」の名に相応しい村人のありがたい手助けで、数日前の台風により流されていた板橋を別の板橋に替えてもらい、ようやく雪野寺目指して竜王山に分け入る正子。京都の宿のおかみ、編集者、ドライバーらとともに突如拓けた原っぱでお弁当を頬張りながら、そこから見えた風景を前に彼女は、それまで結論を導き出せないまま胸中にわだかまっていた疑問にひとつの答えを与えます。「天智天皇が薬狩をしたのは、雪の山に間違いない」、と。
かりに大海人皇子が袖を振ったとしても、ここなら必ず見ることが出来る。おそらく天皇の行在所は、山の中腹の寺が建っているあたりにあり、額田王がそこから眺めていたとすれば、一幅の絵になる。歌の姿が大きく、動きがあるために、広々とした野べを想像しがちだが、万葉の歌の場合、現実の舞台の方は極く小さいのがふつうである。
(白洲正子『近江山河抄』、129頁)
万葉の人々が一千数百年も前に鹿を追い、薬草を摘んだ光景が、そして何より、山腹から見つめる額田王自身に正子が自らを擬するかのように身を寄り添わせながら、この時、彼女の瞳に大海人皇子その人の姿が映っていなかったといったい誰が言えるのでしょうか。
「未知の国」近江を巡る正子の旅はさらに続けられます、そしてその旅の同行者である私たちもまた「近江」がいつの間にか「親しい国」になっていることに驚くのです。
毛利志満コラム第一回目の「白洲正子と近江、蒲生野」はいかがでしたでしょうか。万葉の人々が優雅に狩りに興じ、睦言を交わし合った蒲生野、そこはまさに近江牛の故郷です。鈴鹿山系から流れる野洲川、日野川、愛知川の清らかな水と肥沃な大地、そして澄み切った空気に育まれた近江牛を口に運ばれたとき、万葉人の艶やかな姿と正子の執念と言ってもよい探究心にわずかでもみなさまの想いが馳せられたならば、それは「近江牛から近江の食文化へ」という毛利志満の目指す食と文化の橋渡し役という役柄も、不器用ながら少しは演ぜられたと言えるのかもしれません。
なお、今回のコラムの背景として使用している広がる平野と山並みの写真は、まさに正子が見たであろう雪野山からの風景です。
毛利志満コラム、次回は「高村光太郎「米久の晩餐」の世界」と題して、明治時代にその名を馳せ、一世を風靡した毛利志満の原点「米久」について、そこに流れていた往時の賑やかな時間にしばし旅をしたいと思います。